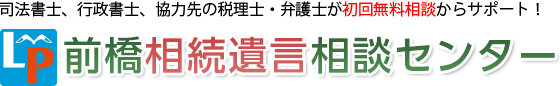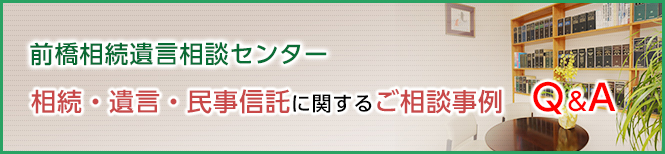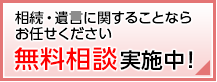2020年03月02日
Q:相続財産が全て他人に渡ってしまいそうです。何か手はありませんか?(前橋)
前橋に住んでいた父が病気で亡くなり、遺産相続の話になりました。相続人は母と私の2人なので、前橋の実家は母が受け継ぎ、貯金のいくらかを私にも分配するという話でまとまっていました。しかし、遺品整理をしていると遺言書が見つかり、そこには全財産を他人に渡すと書かれていました。父は生前に釣りを趣味としていて、元気だったころ良く川へ出かけていたのですが、その時に知り合った川の環境保持活動を行っている方へ渡したいとのことです。私も母も、父の遺言を尊重したい気持ちの反面、前橋の実家はまだ母が住んでいますし、貯金もいくらか残してもらえないと生活が苦しくなるのではと心配です。うまく解決できるようアドバイスをいただきたいです。(前橋)
A:遺留分侵害額の請求をすることで、相続財産の一部を受け取ることができます。
被相続人は遺言を残すことで自分の財産をどうするかを決められます。
遺言書に記せば相続人以外にも財産を渡すことが可能となり、これを「遺贈」と言います。相続の際は故人の遺志を尊重するため遺言書に記載されている内容が優先されますが、現実的に考え、残された遺族が何も相続できないとなるとトラブルになりかねません。
今回の前橋のご相談者様のケースのように、全財産を他人に遺贈するというような遺言書等が残されている場合、残された家族が困らないように、民法では相続財産の最低限度の取り分の割合が定められています。この割合を遺留分と言い、配偶者と子ども(直系卑属)、父母(直系尊属)に限定して認められています。つまり、法定相続人のお母様とご相談者様には遺留分がありますから、遺言書に全財産を他人へ渡すと記載があったとしても、この遺留分相当分については請求する権利を持っています。
なお、遺留分は自動的に手に入るわけでは無いため、受遺者に対して、遺留分侵害額を請求しなければなりません。今回のケースの場合、この請求は“遺留分の侵害を知った日から1年以内”に行う必要がありますのでご注意ください。
このように遺言書によって相続人以外の人物へ遺贈される可能性のある場合には、相続トラブルに発展しやすいと言えます。こういったケースでお困りの方はなるべく早めに前橋相続遺言相談センターにご相談下さい。トラブルになる前に、専門家としてサポートをさせて頂きます。初回のご相談は完全無料ですので少しでもご不安なことがございましたらお気軽にお問い合わせください。前橋の皆様に寄り添って相続をサポート致します。
2020年02月13日
Q:遺言書に書かれていない財産があったのですが、どうしたらいいでしょうか。(前橋)
前橋に住んでいた父が2カ月ほど前に亡くなりました。葬儀なども無事に終わり、落ち着いてきたので、実家に遺産整理をしに行ったところ遺言書を発見しました。父が相続手続きの際に、親族同士でトラブルにならないように、遺言書を残してくれたようです。遺言書は勝手に開封してはいけないと叔母から言われたので、家庭裁判所に検認をしてもらい、開封をしました。開封後、遺言書に沿って遺産整理をしていたのですが、手続きを進めるなか父が亡くなる少し前に購入した前橋の不動産が遺言書に書かれていないことに気づきました。この遺言書に記載されていない不動産はどのように手続きを進めれば良いのでしょうか。(前橋)
A:遺言書に書かれていない遺産は遺産分割で誰が相続するか決めます。
最初に、お父様が相続財産を把握しきれず、遺言書に「記載のない財産についての扱い」が書いてある場合もありますので、そういった項目について書かれていないかもう1度確認をしてみてください。もし、「記載のない財産についての扱い」が書かれていた場合は、その記載内容に沿って相続手続きを進めてください。特にそういった扱いについての内容が書かれていない場合は、その財産の相続について相続人全員で遺産分割協議を行い、合意した内容をもとに、遺産分割協議書を作成します。また、遺産分割協議書は手書きでもパソコンでも作成でき、形式や書式、用紙などの規定もありません。ただし、内容を確認、合意した後に相続人全員に実印で署名押印をしてもらい、印鑑登録証明書を準備してもらう必要があります。なお、不動産の登記変更の時にも、この遺産分割協議書が必要になります。
遺言書の作成は相続において非常に大切な生前対策の一つですので、専門家に相談することをおすすめいたします。相続手続きは個人で行うこともできますが、手続きを進めていくと、ご不明点も出てくるかと思います。前橋相続遺言相談センターでは、前橋にお住まいの皆さまからの遺言書の作成に関するご相談も数多くいただいております。手間暇をかけて書いたとしても、法律上無効となる遺言書は、全く効力を持たないものとなってしまいます。遺言書の作成を検討されている方は、お気軽に前橋相続遺言相談センターの無料相談をご活用ください。皆様のお問い合わせを心よりお待ちしております。
2020年01月14日
Q:弟が亡くなり、義理の妹は妊娠中です。お腹の子も相続人になりますか?(前橋)
前橋在住の40代の主婦です。相続についてご相談があります。結婚して数年経つ弟が数週間前に事故で亡くなりました。葬儀は前橋市内で行いましたが、葬儀の席で弟の妻である義理の妹から相談を受けました。義理の妹は現在妊娠中で、まだ生まれていないお腹の子は相続人にあたるのか知りたいという相談でした。かつて前橋に住んでいた私たちの両親は二人ともだいぶ前に亡くなっております。
私なりに調べたところ、お腹の子供に相続する権利がなければ、義理の妹と私が相続人になるかと思います。弟の遺産がどのくらいなのかは詳しくは分かりませんが、私の気持ちとしては、今後生まれてくる弟の子が遺産を相続して、母子家庭となる義理の妹のため、弟の遺産が少しでも生活の足しになればいいと思っています。(前橋)
A:妻とお腹の子の2人が相続人となり、出生してから遺産分割協議をします。
被相続人が亡くなった際に相続人が妊娠中であった場合、民法により胎児も相続人となります。基本的に権利能力は生まれたときに初めて有することになりますが、相続に関しては民法886条1により「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」と定められているからです。ただし注意が必要なのは、万が一死産となった場合です。死産となってしまった場合は相続人として扱われず、最初からいなかったものとみなされます。その際には義理の妹様とご相談者様が相続人となりますので、無事に出生するのを待ってから遺産分割協議を進めます。よって今回のご相談者様のケースにおきましても、お腹の子は相続人とみなされます。相続人は妻と子供の2人となりますので、ご相談者様のご希望通りに相続は進むでしょう。
しかしながら、万が一お腹の子が死産となり、ご相談者様が相続人となった場合でもご相談者様が相続放棄を行うか、もしくは義理の妹様が全てを相続するという内容に同意し、遺産分割協議書を作成すれば、ご相談者様のご希望通りに進むかと思われます。
相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内が期限ですので注意してください。今回の場合は、ご相談者様は義理の妹様のお腹の子の死産により相続人となるため、ご相談者様がお腹の子の死産を知った時から3か月以内ということになります。
また、未成年者の相続人には法定代理人を立てなければなりません。通常未成年者の法定代理人は親である義理の妹様ですが、今回は義理の妹様も相続人であるため利益相反の立場になりますので、出生後の遺産分割協議の際には、家庭裁判所にて特別代理人を選任してもらう必要があります。
相続についてのご不明点などは後々のトラブル等を避けるためにも専門家に頼りましょう。前橋相続遺言相談センターは、行政書士・司法書士が在籍し、相続手続きに関する幅広いお困り事に対応が可能でございます。まずはお気軽に無料相談までご相談ください。ご相談内容により、必要な場合にはパートナーの税理士や弁護士と連携して対応できる体制を整えておりますので、安心してお任せください。
初回のご相談は、こちらからご予約ください

平日:9時00分~19時00分 土日は要相談
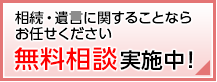
前橋相続遺言相談センターでは、初回無料相談を受け付けております。また、事務所は前橋市にございますが出張面談も受け付けておりますので、高崎、伊勢崎、みどり市の方々もお気軽にお問い合わせください。前橋で相続・遺言・民事信託のご相談ならお任せください。